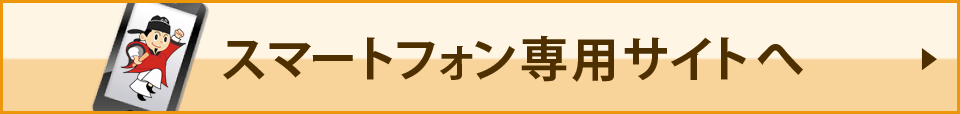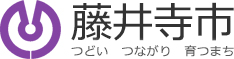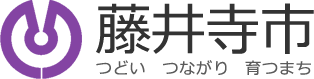高額療養費について
更新日:2024年02月20日
1カ月に支払った医療費の一部負担金が一定額を超えたときは、申請により超えた分が「高額療養費」として支給されます。限度額は、『70歳未満の方』と『70歳以上75歳未満の方』とでは異なり、また、所得区分によっても異なります。
70歳未満の方
自己負担限度額(月額)
ア.所得901万円超 252,600円+(医療費-842,000円)×1%
〈直近12ヵ月の間に4回以上適用されるときは、4回目から140,100円〉
イ.所得600万円超901万円以下 167,400円+(医療費-558,000円)×1%
〈直近12ヵ月の間に4回以上適用されるときは、4回目から93,000円〉
ウ.所得210万円超600万円以下 80,100円+(医療費-267,000円)×1%
〈直近12ヵ月の間に4回以上適用されるときは、4回目から44,400円〉
エ.所得210万円以下 57,600円
〈直近12ヵ月の間に4回以上適用されるときは、4回目から44,400円〉
オ.市民税非課税世帯 35,400円
〈直近12ヵ月の間に4回以上適用されるときは、4回目から24,600円〉
※ 所得とは、基礎控除後の「総所得金額等」に当たります。
※ 所得の申告がない場合は「ア.所得901万円超」扱いになります。申告忘れにご注意ください。
自己負担額の計算方法
- 月の1日から末日までについて計算します。
- 2つ以上の病院・診療所にかかった場合は、別々に計算します。
- 同じ病院・診療所でも、歯科は別計算です。また、外来・入院も別計算します。
- 食事代や差額ベッド代など保険適用にならないものは支給対象外です。
- 途中で保険の種類が変更になった場合は別計算です。
申請について
医療機関等でお支払いをされてから、約3~4ヵ月後に支給対象の方には通知をお送りします。
窓口での支払いが限度額までとなるとき
70歳未満の方について、外来・入院とも、「限度額適用認定証」を提示していただきますと、一医療機関の窓口での支払いは自己負担限度額までとなります。
「限度額適用認定証」が必要な場合は、あらかじめ保険年金課の窓口で交付申請をしてください。
※健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカードを利用し、医療機関への限度額情報の提供に同意した場合は、限度額適用認定証の提示は必要ありません。
「限度額適用認定証」等は申請月の初日から適用されます。申請月の前月以前の分については、さかのぼって適用されませんのでご注意ください。また、保険料の納付状況により交付できない場合もあります。
申請に必要なもの
- 身分を証明するもの
- 認定証が必要になる方の保険証
- 個人番号がわかるもの(通知カード・個人番号カード 等)
※代理の方が来られるときは、世帯主からの委任状・代理の方の身分を証明するもの・世帯主および対象となる方の個人番号がわかるもの(通知カード・個人番号カード 等)も併せてお持ちください。
70歳~74歳の方
自己負担限度額(月額)
・ 現役並み所得3の方(課税所得690万円以上)
外来+入院 252,600円+(医療費-842,000円)×1%
(直近12ヶ月の間に4回以上適用されるときは、4回目から140,100円)
・ 現役並み所得2の方(課税所得380万円以上)
外来+入院 167,400円+(医療費-558,000円)×1%
(直近12ヶ月の間に4回以上適用されるときは、4回目から93,000円)
・ 現役並み所得1の方(課税所得145万円以上)
外来+入院 80,100円+(医療費-267,000円)×1%
(直近12ヶ月の間に4回以上適用されるときは、4回目から44,400円)
・ 一般の方(市民税課税世帯で、現役並み所得の方以外)
外来(個人ごと) 18,000円(年間144,000円上限)
外来+入院(世帯単位) 57,600円
(直近12ヶ月の間に4回以上適用されるときは、4回目から44,400円)
・ 低所得者2の方(注釈:1)
外来(個人ごと) 8,000円
外来+入院(世帯単位) 24,600円
・ 低所得者1(注釈:2)
外来(個人ごと) 8,000円
外来+入院(世帯単位) 15,000円
(注釈:1) 同一世帯の全員が市民税非課税で、低所得者1以外の被保険者。
(注釈:2) 同一世帯の全員が市民税非課税で、その世帯全員の個々の所得が0円(ただし、公的年金等の控除額は80万円として計算)、または、同一世帯の全員が市民税非課税で、老齢福祉年金を受給している被保険者。
自己負担額の計算方法
- 月の1日から末日までについて計算します。
- 外来は個人ごとにまとめて計算します。入院を含む自己負担は世帯内の対象者を合算して計算します。
- 病院・診療所、歯科の区別なく合算して計算します。
- 食事代や差額ベッド代など保険適用にならないものは支給対象外です。
申請について
医療機関等でお支払いをされてから、約3~4か月後に支給対象の方には通知をお送りします。
窓口での支払いが限度額までとなるとき
現役並み所得3、一般に該当する方は、高齢受給者証を提示することで、一医療機関での支払いが自己負担限度額までとなります(限度額適用認定証の発行の必要はありません)。
現役並み所得1・2、低所得者1・2に該当する方は「限度額適用認定証」が必要となりますので、あらかじめ保険年金課の窓口で交付申請し、「限度額適用認定証」と高齢受給者証を提示してください。
※健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカードを利用し、医療機関への限度額情報の提供に同意した場合は、限度額適用認定証の提示は必要ありません。
「限度額適用認定証」は申請月の初日から適用されます。申請月の前月以前の分については、さかのぼって適用されませんのでご注意ください。また、保険料の納付状況により交付できない場合もあります。
申請に必要なもの
- 身分を証明するもの
- 認定証が必要になる方の保険証
- 個人番号がわかるもの(通知カード・個人番号カード 等)
※代理の方が来られるときは、世帯主からの委任状・代理の方の身分を証明するもの・世帯主および対象となる方の個人番号がわかるもの(通知カード・個人番号カード 等)も併せてお持ちください。
問合先 保険年金課国民健康保険担当
- お問い合わせ
-
健康福祉部 保険年金課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所1階2番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1177 (国民健康保険担当)
072-939-1181 (国民年金担当)
072-939-1183 (収納担当)
072-939-1186 (福祉医療担当)
072-939-1353 (保健事業担当)
ファックス番号:072-939-0399
メールフォームでのお問い合せはこちら
- みなさまのご意見をお聞かせください
-