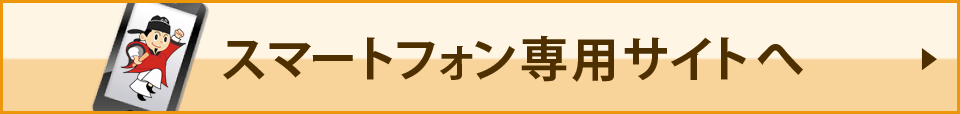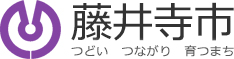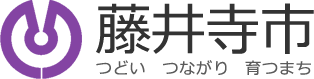児童扶養手当
更新日:2024年11月01日
児童扶養手当制度のご案内
父母の離婚など(父又は母に一定程度の障害がある場合を含む)で『父又は母と生計を同じくしない児童が養育されている家庭』の生活の安定と自立を助けるために、児童の父又は母や父又は母に代わってその児童を養育しているかたに支給します。
支給対象者
次のいずれかにあてはまる18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(下記参照)を、監護している母、児童を監護し、かつ生計を同じくする父、又は養育者が受給できます。
心身に中度(特別児童扶養手当2級に該当する程度)以上の障害がある児童の場合は、20歳未満の児童が対象となります。
- 父母が離婚した児童 (離婚)
- 父又は母が死亡した児童 (死亡)
- 父又は母が一定の障害の状態にある児童 (障害)
- 父又は母の生死が明らかでない児童 (生死不明)
- 父又は母に引き続き1年以上遺棄されている児童 (遺棄)
- 父又は母が申立によりDV防止法による保護命令を受けた児童(保護命令)
- 父又は母が引き続き1年以上拘禁されている児童 (拘禁)
- 母が婚姻によらないで出産した児童(未婚)
上記の場合であっても、次のいずれかに該当する場合は、支給されません。
- 父又は母に配偶者(内縁関係、同居など婚姻の届出をしていないが社会通念上事実上婚姻関係と同様の事情にある者も含む)があり、実質上の母又は父が存在するような場合
- 手当を受けようとする人、対象となる児童が日本に住んでいない場合
- 児童が児童福祉施設(母子生活支援施設・保育所・通園施設を除く)又は障害者福祉施設などに入所している場合
- 児童が里親に委託されている場合
手当の額
受給者及び扶養義務者等(下記参照1)の所得に応じて、次の額になります。
| 対象児童数 | 支給区分 | ||
| 全額支給 |
一部支給 (下記参照2) |
全部停止 (下記参照2) |
|
| 1人目 | 46,690円 | 46,680円~ 11,010円 |
0円 |
| 2人目以降 (1人につき) |
11,030円 | 11,020円~ 5,520円 |
|
上記金額は、令和7年4月分からものです。
手当額は、「物価スライド制」の適用により、改定される場合があります。
(下記参照1)扶養義務者等について
手当を受けようとするかたの配偶者(一定程度の障害の状態にある場合)、同住所に住民登録をしている直系血族もしくは兄弟姉妹、又は孤児の養育者をいいます。
(下記参照2)一部支給・全部停止について
受給者の前年の所得(下記「所得の計算方法について」参照)が、下表「所得制限限度額表」の全部支給の所得制限限度額以上のかたは、その年度(11月~翌年10月)手当の一部又は全部が支給停止になります。
一部支給の額は、下記「一部支給の手当額計算方法」を参照ください。
なお、扶養義務者等の所得額が、限度額以上の場合は全部が支給停止になります。
新規認定の場合、1~9月請求のときは前々年の所得、10月~12月請求のときは前年の所得で判定します。
所得制限限度額
| 扶養親族等の数 | 父または母または養育者 |
扶養義務者等の 所得制限限度額 |
|
| 全部支給 | 一部支給 | ||
| 0人 | 69万円未満 | 208万円未満 | 236万円未満 |
| 1人 | 107万円未満 | 246万円未満 | 274万円未満 |
| 2人 | 145万円未満 | 284万円未満 | 312万円未満 |
| 3人 | 183万円未満 | 322万円未満 | 350万円未満 |
| 以降1人につき | 38万円加算 | ||
※上記の所得制限限度額は、令和6年11月分~の制度改正後の金額です。
なお、所得税法に規定する次の扶養義務者等がある場合は、上記の限度額に1人につき次の金額を加算した額が『所得制限限度額』となります。
| 受給者本人 | 扶養義務者等 | |
| 特定扶養親族等 (16歳以上23歳未満の扶養親族) |
1人につき 15万円 |
老人扶養親族(70歳以上の扶養親族) 1人につき6万円 ※扶養親族がすべて70歳以上の場合は1人を除く |
| 老人控除対象配偶者 (70歳以上の控除対象配偶者) |
1人につき 10万円 |
|
| 老人扶養親族 (70歳以上の扶養親族) |
||
所得の計算方法について
所得額=『(年間収入額)-(必要経費:給与所得控除額等)』+『養育費(下記参照4)の8割』-諸控除(下記参照5)
(下記参照4)養育費
母または父もしくはその監護する児童が、その監護する児童の父又は母から、その児童の養育に必要な費用として受け取っている費用をいいます。
(下記参照5)諸控除
所得から控除できる項目は、地方税法に規定する控除を受けた場合に次の額を控除します。
| 受給者及び扶養義務者共通 | 受給資格者が 父又は母以外の場合のみ |
||||
| 控除項目 | 控除額 | 控除項目 | 控除額 | 控除項目 | 控除額 |
| 一律控除 | 8万円 | 配偶者特別控除 | 住民税で 控除された額 |
寡婦控除 (※1) |
27万円 |
| 障害者控除 | 27万円 | 医療費控除 | |||
| 特別障害者控除 | 40万円 | 小規模企業共済等掛金 | ひとり親控除 (※1) |
35万円 | |
| 勤労学生控除 | 27万円 | 雑損控除 | |||
| 土地譲渡等に係る特別控除 | 最大5000万円 | ||||
※1 受給者が対象児童の母または父の場合は、寡婦控除・ひとり親控除は適用されません。
※2 詳細はお問い合わせください。
『一部支給の手当額の計算方法』
所得に応じ、次の算式により10円単位で手当月額が決まります。対象児童が2人以上いる場合は2人目以降の額を合算した額となります。
|
1人目 |
46,680円 -〈(受給者所得額 - 所得制限限度額(全部支給))× 0.0256619〉 |
|
2人目以降 |
《11,020円 -〈(受給者所得額 - 所得制限限度額(全部支給))× 0.0039568〉》 × 2人目以降の対象児童数 |
※___は10円未満四捨五入
年金の併給について
障害基礎年金以外の公的年金を受給されている方は、公的年金の額が児童扶養手当額を下回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できます。なお、障害基礎年金等を受給されている方は、令和3年3月分以降、障害基礎年金の子の加算部分の額が児童扶養手当の額を下回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになりました。
※児童扶養手当を既に受給している方で、新たに公的年金等を受給するようになった場合、児童扶養手当の金額が年金を支給した時点に遡って変更になりますので、速やかに届け出てください。届出が遅れた場合、手当を遡って返還していただく場合があります。
申請方法について
離婚等によりひとり親家庭になった場合は、こども育成課窓口まで必要な書類等を確認・相談のうえ、手続き(認定請求)をして下さい。
必要書類等
- 請求者及び児童の戸籍謄本
戸籍謄本は、認定請求をする日から1ヶ月以内に交付されたもの
戸籍の改製などにより、現在の戸籍謄本に受給資格要件(離婚の事実など)の記載がない場合は、受給者要件(離婚した事実など)が記載された改製原戸籍の謄本等も必要になりますので、ご注意ください。戸籍謄本を請求される際に、戸籍謄本発行窓口で、記載内容等をご確認ください。
- 年金手帳
- 印鑑
- 振込先の通帳等(請求者本人の名義に限ります)
その他、状況に応じて必要な書類がありますので、申請前に必ず児童扶養手当担当課へご相談ください。書類に不備があると、受付できませんのでご注意ください。
児童扶養手当の認定を受けられた人へ
申請が認定されると請求された月の翌月分から支給されます。
支払は年6回、2ヶ月分の手当額を受給者の指定した金融機関の口座へ振込みます。
|
支給日 |
支給対象月 |
備考 |
|
1月11日 |
11月分~12月分 |
支給日が土・日・祝日にあたるときは、その直前の金融機関が営業している日となります |
|
3月11日 |
1月分~2月分 |
|
|
5月11日 |
3月分~4月分 |
|
|
7月11日 |
5月分~6月分 |
|
| 9月11日 |
7月分~8月分 |
|
| 11月11日 | 9月分~10月分 |
※2019年11月より隔月となりました。
詳細はこちら「児童扶養手当」が年6回払いになります(厚生労働省)(PDF:131.1KB)
証書の交付について
- 認定に伴い、「児童扶養手当証書」を交付します(“全部停止"となる場合を除く)。
- 期限は、原則次の10月末日までです(「有期認定」のかたを除く)。
- なお、証書を他人に譲り渡したり、担保にすることはできません。
証書の更新は、毎年の「現況届」の審査結果により引き続き受給資格を有し支給のあるかたに対して更新します。
証書は現況届をはじめいろいろな届を出すときに必要ですので、大切に保管してください。
必要な届出について
毎年8月に現況届の提出が必要です
毎年8月1日から8月31日の間に現況届を提出しなければなりません。
この届によって手当を引き続き受けられる資格があるのかどうか審査しますので、この届を提出しないと手当の支給が差し止めになります。7月末に必要書類を記載した案内を送付します。
- なお、所得制限によって、手当が全部停止されている人についても、提出をしていただかなければなりません。
- 現況届を2年間続けて出さないままにしておくと、手当を受ける資格がなくなります。
その他必要な届出について
生活されている状況や、戸籍等に変更があった場合には、すぐに届け出てください。(主な例は次のとおりですが、変更があった場合はほとんどの場合、届出が必要ですので、お問い合わせください。)
届出は事由が発生した時点で速やかに提出してください。届出が遅れた場合、手当の支給が出来なくなったり、手当を返還していただく場合があります。
- 婚姻した時(生活を共にしている等の事実婚を含む)住民票上、世帯を分離していても同住所である場合、その他事実上の婚姻と認められる場合は、これに該当していると推定します
- 児童を監護又は養育しなくなった時(児童が児童福祉施設に入所した時を含む)
- 公的な年金等を受けることができるようになった時、又は、給付の額が変わったとき
- 扶養義務者(父母・祖父母・子・孫などの直系血族と兄弟姉妹)と同居(1太字参照)するようになった時、又は、別居するようになった時
- 氏名や住所を変更した時
- 支払金融機関を変更する時
- 手当を受ける理由が変更になった時
- 対象児童が増えた時
- 受給者や対象児童が死亡した時
- 受給者や扶養義務者の所得の更正(修正申告)をした時
- 証書をなくしたり、破ったりした時
支給期間等による一部支給停止制度と適用除外届について
平成14年の母子及び寡婦福祉法等の改正により、母子家庭への支援については、従来の「児童扶養手当中心の経済支援」から「就業・自立に向けた総合的な支援」への転換が図られました。
その一環として、児童扶養手当については、「離婚時における生活の激変を緩和するための給付」へと位置付けが見直され、『支給期間等による一部支給停止措置』が導入されました。
手当の一部支給停止制度について
児童扶養手当の受給開始から5年等を経過した場合※で、受給資格者やその子ども等の障害・疾病等により就業が困難な事情がないにもかかわらず、就業意欲がみられないかたについては、児童扶養手当の支給額の2分の1を支給停止とすることになっています。
※「5年等を経過した場合」について:
次のいずれか早いほうを経過する場合をいいます。
- 支給開始月の初日から起算して5年
- 手当の支給要件に該当するに至った日の属する月の初日から起算して7年
ただし、手当の認定請求(額改定請求を含む。)をした日において3歳未満の児童を監護する場合は、この児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年を経過したときとします。
一部支給停止の適用除外事由について
上記に該当することとなったかたのうち、下記「一部支給停止適用除外事由」※に該当する場合には、一部支給停止措置(手当の2分の1の減額)は行われません。
※「一部支給停止適用除外事由」:
次のいずれかの事由に該当する場合をいいます。
- 就業している場合
- 求職活動等の自立を図るための活動をしている場合
- 身体上又は精神上の障害がある場合
- 負傷又は疾病等により就業することが困難である場合
- 受給者が監護する児童又は親族が障害、負傷、疾病、要介護状態等にあり、受給者が介護する必要があるため、就業することが困難である場合
一部支給停止の適用除外措置を受けるための手続きについて
この適用を受けるためには、「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」に証明書類を添付の上、市役所こども育成課まで提出することが必要です。
適用除外事由に該当することが確認できた場合は、「支給停止適用除外」となり、現在受けている手当額を継続して受給することができます。
所得の状況や家族の状況に変動があった場合における一部支給停止措置は、この限りではありません。
なお、該当した後は、毎年1回提出が必要となります。(「現況届」と併せて提出していただくことになります。)
児童扶養手当の適正受給にご協力ください
児童扶養手当は、父又は母と生計を共にしないひとり親家庭等※で児童を養育している方に支給します。
※1 父母両方と生計を共にしているが、いずれか1人に一定の障害がある場合を含みます。
※2 戸籍上婚姻をしていなくても、同居し生計を共にしているなど、実態として夫婦関係が認められる等の場合は、児童扶養手当の支給要件に該当しない場合があります。
手当を不正に受給されると、その間に受給された手当はさかのぼって返還していただく必要があります。場合によっては罰せられる可能性もありますので、支給要件をよく確認の上、正しく受給していただきますようお願いいたします。
制度についてご不明な点がございましたら、こども育成課までお問い合わせください。
- お問い合わせ
-
こども未来部 こども育成課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所2階23番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1126 (入所担当)
072-939-1161 (育成担当)
ファックス番号:072-939-1128
メールフォームでのお問い合せはこちら
- みなさまのご意見をお聞かせください
-