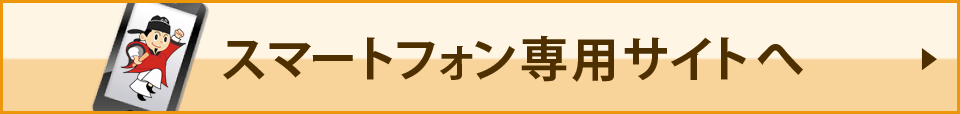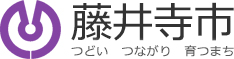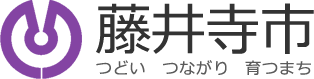巨大古墳の築造年代2(No.163)
更新日:2020年05月06日
『日本書紀』によれば、雄略天皇(倭王武)は457年に即位し、崩年は23年後の479年とします。しかし、『宋書』では倭王興が460年と462年に遣使していますので、ぴったりとは合いません。『古事記』干支を重視する菅政友さんによれば、崩年は489年だとします。
いずれが正しいのか、両方誤っているのか、ただちに結論はでないのですが、倭王武の墳墓は、後を継いだ王によって5世紀末ごろには完成したと見なしてもいいのではないかと考えます。そのころに完成した巨大古墳をさがしていくと、岡ミサンザイ(仲哀陵)古墳に行き着くのです。
倭の五王の墳墓を今一度整理して申し上げると、
讚の先王の墳墓=誉田御廟山(応神陵)古墳
讚の墳墓=大仙(仁徳陵)古墳
珍の墳墓=土師ニサンザイ古墳(陵墓参考地)
済の墳墓=市野山(允恭陵)古墳
興の墳墓=軽里大塚(白鳥陵)古墳
武の墳墓=岡ミサンザイ(仲哀陵)古墳
となります。なかなかいい線だと思っているのですが、さあどうでしょう。
この推定からすると、大王の陵地が古市→百舌鳥→百舌鳥→古市→古市→古市と入れ替わったことになります。『宋書』では讚と珍が兄弟、済と興・武は父子の関係だと伝えています。『梁書』では彌(珍)と済が父子だとします。つまり、倭の五王は血族関係にあった人物だとされているのです。その王の陵地が百舌鳥、古市の両方に造られていたとすれば、両大古墳群が単純にそれぞれが特定集団の奥津城(おくつき)だと理解することはできなくなります。
考えられることは、百舌鳥と古市は一つの最有力集団の意思のもとに形造られた、または水野正好さんが主張されるように大王墳は妃の出身地に造られた、あるいは大王を推載する有力集団が自らの領有地に大王墳を造った、などがあるでしょう。ただ、後二者はその証明がかなり難しいと思います。したがって、最初の想定が一番スムーズな理解だと考えているのですが、どうでしょうか。
ここで、これまで雄略天皇の墳墓と考えられてきた二つの古墳について少し検討を加えておきたいと思います。
一つは羽曳野市にある島泉丸山古墳です。この古墳は現在雄略天皇陵に治定されている径76メートルの円墳です。その根拠は、『古事記』に「河内(かふち)之多治比高鸇(たぢひたかわし)」、『日本書紀』および『延喜式』に「丹比高鷲原」という陵地の記載があることによります。河内→丹比→高鷲と地域を絞っていくと島泉丸山古墳に行き着くというのです。しかし、治天下大王として名をはせた雄略天皇の墳墓としてはあまりに小規模でかつ円墳だということで早くから疑問がでていました。
『大日本地名辞書』を著した吉田東伍さんは、古市古墳群と百舌鳥古墳群の中間に築かれた巨大な前方後円墳河内大塚古墳こそ雄略天皇陵として相応しいとしました。河内大塚古墳は墳丘長335メートルもあって全国第5位の大きさを誇っていて、規模からするとなるほど雄略天皇陵として十分な資格があります。これが第二の候補となりました。
しかし、この両墳には築造時期の面で問題を残しています。島泉丸山古墳は羽曳野市教育委員会が行った近辺の発掘調査で出土した円筒埴輪をみると、5世紀中葉を下ることはなさそうなのです。一方、河内大塚古墳では、後円部の中段に露出している大石に注目が集まります。
(つづく)
2003.10

現雄略天皇陵の島泉丸山古墳(北から撮影)
- お問い合わせ
-
教育委員会事務局教育部 文化財保護課
〒583-8583
大阪府藤井寺市藤井寺3丁目1番20号アイセルシュラホール2階
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1419 (文化財担当、世界遺産担当)
ファックス番号:072-952-7806