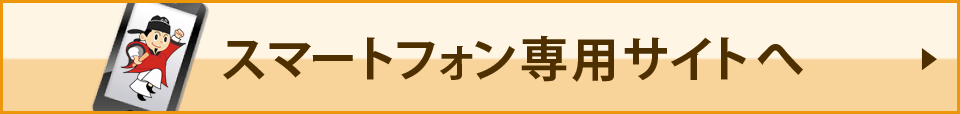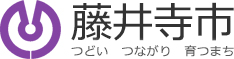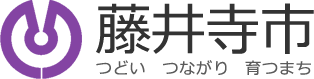市政運営方針
更新日:2025年02月21日
令和7年度市政運営方針
令和7年第1回定例市議会の開会にあたり、新年度の市政運営につきまして、所信の一端を申し述べたいと存じます。
はじめに
今年の干支である「巳年」には、脱皮を繰り返し大きくなる蛇のように「再生と成長」の意味が込められています。本市においても、「第六次藤井寺市総合計画」に掲げられた、まちの将来像である「~人と歴史が活きる未来へ~ 笑顔と活気に満ちた快適なまち ふじいでら」の実現に向けて、飛躍する一年にしたいと考えます。
この4月には大阪・関西万博が「いのち輝く未来社会のデザイン」をテーマに開催されます。1970年の大阪万博は、戦後の復興を遂げ、高度経済成長のシンボル的なイベントでありました。今回の万博も人類が直面する課題解決のために、様々な先端技術が披露される意義深いものであり、内外の多くの方が訪れます。この絶好の機会を捉え、市民、団体、事業者の皆様と一体となり、万博会場に出向き、大阪ウィークなどの催しに参画します。世界遺産を擁する本市の歴史文化や魅力を発信し、誘客、にぎわいの創出、地域の活性化へとつなげたいとの思いが漲ります。
また、子どもたちにとって、万博は、世界各国の文化や未来社会を体験できる貴重な機会です。万博を通じ、自らの将来に目標を掲げ、チャレンジする意欲が持てるよう、府実施の万博招待事業に加えて、4歳から17歳までの子どもたちを対象に無料招待を行います。
万博で得られるこうした有形・無形の財産を次世代へと継承し、藤井寺市の未来を築く礎の一つにしたいと存じます。
さらに、社会情勢に目を転じると、急激なエネルギー・食料品価格等の物価高騰が続いており、市民生活に大きな影響を与えています。この状況に対処するため、令和7年度も、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、住民税非課税世帯に加え住民税の均等割のみ課税世帯を対象とする給付金事業をはじめ、市立小中学校の給食費の一部助成、市民の生活支援と事業者への経済波及効果をもたらす商品券事業などを実施します。
こうした対応の一方で、憂慮すべきことは、本市の財政状況です。令和5年度一般会計決算では財政調整基金を取り崩し、人事院勧告の実施を令和7年1月からとするなど、厳しい状況にあります。今後の市政運営にあたっては、限られた資源と資産を最大限有効に活用し、困難な行政課題に取り組まなければなりません。
それでは、令和7年度に予定しています主な施策について、本市の総合計画の5つの施策の柱に沿い、概要を説明申し上げます。
5つの施策の柱
1 地域の人や資源を活かし、にぎわいと活力を創出する
令和7年4月に、アイセルシュラホールが「にぎわい・まなび交流館」としてリニューアルオープンします。
リニューアルに際し、多くの企業や有志の方々から寄附等のご協力をいただきました。心より感謝を申し上げます。ご協力下さった方々を含め、多くの方々に愛される施設へと今後、成長させてまいります。
新たなアイセルシュラホールは、これまでの生涯学習機能だけでなく、観光拠点機能も兼ね備えた施設です。観光案内や特産品販売に加えて、有名なフィギュア制作会社による精巧で迫力ある前方後円墳のジオラマ、本市の貴重な文化財の鑑賞や歴史文化にちなんだコンテンツが体験でき、市民の皆様をはじめ、来館者が楽しみ交流していただける、にぎわいの場を創出します。
令和7年は貴重な本市の歴史資産である葛井寺の本尊、国宝千手観音坐像の開眼1300年の節目にあたり、大坂夏の陣として歴史的にも有名な道明寺合戦から410年を迎えます。これら古の来歴が未来へ伝承される取組について、地域の団体と連携してまいります。
また、本市が世界に誇る世界遺産「百舌鳥・古市古墳群」の歴史的・文化的価値を保持しつつ、その魅力が最大限発揮できるように古市古墳群の適切な保存と活用に注力します。羽曳野市と共同で策定した「史跡古市古墳群整備基本計画」の整備方針に基づき、古墳の価値と保存の必要性を多くの人々に伝えます。
観光施策に関しては、テレビ番組内での本市のPRをはじめ、保有する観光コンテンツの有効活用、近隣自治体や観光局、民間事業者とも連携したプロモーションなどを展開し、観光客を誘引します。
さらに、観光で訪れるだけでなく、多くの方々に住みたいと思われるような魅力発信も重要です。
全国でも先駆的に収益化を実現した本市公式YouTubeチャンネルを活用し、施策や制度、手続きの解説動画など、市民生活の利便性の向上に資する情報提供を強化します。私自身も動画に出演し、本市が有する特産品やその生産拠点、映えるビューポイントなど、様々な魅力発信に努めます。
観光と共に地域産業の振興も重要です。創業や経営の多角化、技術革新などは、税収増だけでなく、基幹産業育成にもつながる重要な要素です。藤井寺市中小企業振興計画に基づき、「事業者支援補助金」が有効に活用され、成果を生むよう、伴走支援などの取組を進めます。
多様化・複雑化する社会における地域課題の解決には、行政だけでなく、市民・各種団体・事業者をはじめ多様な主体との連携や共創が重要です。そこで、地域活動の活性化をめざし、地域を支える自治会の皆様が安心して活動できるよう、新たに自治会活動等保険制度を採用し、その環境整備に努めるほか、地域課題の解決に取り組む民間企業との共同・連携を積極的に検討します。
また、にぎわいと活力ある社会の中では、一人ひとりが大切にされ、多様性が尊重されることが重要です。性別にとらわれず自分らしさを大切にできる社会の実現に向けた取組を継続していくため、令和7年度に「第5期男女共同参画のための藤井寺市行動計画」の策定を進めます。
2.子どもたちが輝き、生涯にわたり学び・活動する
子どもたちが輝く社会の実現には、子育て世代が将来に夢を持ち安心して子どもを育める環境づくりが、基礎自治体に求められます。子どもたちを取り巻く社会環境は、少子化・高齢化や核家族化の進行により、ライフスタイルや価値観の多様化が進行し、加えて児童虐待やひきこもり、地域社会とのつながりの希薄化など、都市部に顕著な課題も複雑化を呈しています。
これらの問題に対応し、子どもたちが強く、健やかに生まれ育ち、夢を持てる環境づくりをめざし、令和6年4月に設置した「藤井寺市こども家庭センター」において、妊産婦や子ども・子育て世帯への一体的な相談支援を、引き続き進めてまいります。また、令和7年度は子育て等に不安を抱えた子育て家庭に対して、育児支援を実施し、子どもの養育環境を整え、虐待の未然防止を図る「子育て世帯訪問支援事業」を実施いたします。
幼稚園・保育所・こども園は、子どもたちの成長と発達を支援する重要な施設です。市立の幼稚園・保育所につきましては、藤井寺市立幼稚園・保育所再編実行計画(後期計画)の方針に基づき、再編に向けた検討を進めてまいります。また、待機児童解消に向けては、民間保育施設設置・運営事業者の公募を令和6年に行い、定員100名規模の民間保育所の整備事業者を選定しました。令和8年4月の開所に向け施設整備の支援を行ってまいります。
学校施設の環境整備では、保護者からも要望の強いトイレの洋式化を小学校の低学年児童が利用するトイレから順次、着手します。
学校プールについては、設置後50年以上が経過し老朽化が著しいこと、また、安全を確保した水泳授業の実施が教員への大きな負担になっていることから、令和7年度は試行的に一部の小学校の水泳授業を事業者へ委託し、民間のプールで実施します。この試行実施を踏まえて、今後の市立小中学校での水泳授業のあり方や学校プールへの対応について検討を進めます。
小中学校ではGIGAスクール構想を推進しているところであり、更新時期を迎える既存のタブレットは、これまでの実績を踏まえて、児童生徒にとって学習効果が高く、かつ教員にも使いやすい良質なデジタル教材を備えたものを導入し、学校現場における教育DX(デジタル・トランスフォーメーション)のさらなる充実を図ります。
さらに、中学校部活動の地域移行については、教員の働き方改革も含め、持続可能な部活動運営を目標として、合同部活動や外部指導部活動を視野に、引き続き検討を進めます。
地域と共にある学校づくりに向けた「コミュニティスクール」については、モデル校である道明寺南小学校の取組を検証し、新たな地域への導入を検討します。併せて、学校・地域の各種団体・保護者との協力体制をより強く構築するため、地域学校協働活動推進員の配置とともに、地域学校協働本部の設置に向けて、引き続き、地域との連携を図ります。
3.誰もが健やかに暮らし、ともに支え合う
高齢化が進む社会において、市民一人ひとりが生きがいを持って健康で長生きできるまちをめざすためには、市民の健康意識を向上させ、主体的に健康の保持・増進に取り組んでいただくことが肝要です。
各種の健康診査やがん検診を定期的に受診する意識を根づかせ、規則正しい生活習慣づくりに取り組む環境づくりを進めます。その周知等にあたっては、市単体による取組に加え、民間事業者のネットワークも積極的に活用し、健康診査などの受診率の向上が一層図られるよう注力します。
さらに、国民健康保険事業や後期高齢者医療制度の保健事業でも、民間事業者と連携し、減塩食品の推奨など生活習慣病の発症や重症化の予防、オンラインでの健康相談の実施など、被保険者の健康増進についての取組を進めます。
地域福祉の推進に関して、令和7年度は、第4期藤井寺市地域福祉計画の最終年となります。誰もが安心して暮らせるよう、計画を着実に実施するとともに、第5期計画の策定に向け、市民や福祉関係者のご意見をお伺いします。また、障害の有無に関わらず誰もが共生できるまちづくりに向け、障害者基幹相談支援センターの機能強化に取り組みます。
令和7年は、団塊世代の方々が全て75歳以上の後期高齢者になる年です。高齢者が住み慣れた地域で自分らしい暮らしを生涯に渡り続けられるよう、令和6年度にスタートした「第9期藤井寺市いきいき長寿プラン(高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画)」に基づき、社会全体で高齢者を支える仕組みとして、高齢者福祉施策の充実や介護保険事業の円滑な運営等に努めます。また、令和9年度から始まる第10期計画の策定業務にも着手します。
帯状疱疹ワクチンの定期接種については、令和7年度から国が定めた対象者への接種が開始されることから、接種希望者に対し、費用の助成を市の負担で実施します。
4.自然と調和しつつ、災害などから市民を守る安心・安全な環境をつくる
安心・安全な環境をつくるために本市が重視すべき点は、地震、風水害をはじめとする自然災害への適切な対応、そして、次世代も安心・安全に暮らせる環境を引き継ぐゼロカーボンシティの実現です。SDGsへの貢献が地球規模で求められる今日、市民のご理解とご協力を得ながらこれら課題に取り組みます。
令和7年度は防災力強化のため、消防団車庫の建替、府と連携した第3世代の衛星無線等の再整備、新たな備蓄方針に基づく備蓄品の充実などに取り組みます。また、地域における自主防災力の強化に向け、自主防災組織結成の働きかけを継続して行います。
また、昨今の地震のリスクを踏まえ、市民総合体育館及び図書館の耐震補強工事と共に、市民総合体育館については空調整備を行い、施設の環境改善に努めてまいります。
大雨による雨水災害への対応として、老朽化対策に取り組んでいる小山、北條の両雨水ポンプ場の工事を令和7年度も継続します。
地域における防犯活動に対しては、地域の犯罪抑止、地域住民の防犯意識の高まりという観点から、地域の防犯カメラ設置への補助を引き続き実施します。
環境対策では、令和6年度に地球温暖化対策実行計画の事務事業編を見直し、区域施策編の策定に取り組みました。令和7年度はゼロカーボンシティの実現に向け、計画の着実な実行をめざします。
サクラ、モモ、ウメなど主にバラ科の樹木に寄生し枯死させるクビアカツヤカミキリ被害に対しては、従来から適宜対応してまいりましたが、府域内でも年々被害が拡大していることから、国庫補助金も活用しながら、引き続きその対策を進めます。
5.それぞれの地域の良さを活かし、快適で良好な生活空間を形成する
第六次総合計画のスタートに伴い、藤井寺市都市計画マスタープランの改定に取り組みました。本市の土地利用や道路、公園、下水道など都市施設についての基本的な方向性のほか、重要な事業である「都市計画道路八尾富田林線沿道まちづくり事業」を踏まえた市街地形成の方針などを定め、このマスタープランに基づいたまちづくりを令和7年度から推進します。
八尾富田林線沿道のまちづくりに関しては、地権者と共に土地利用の方向性について検討し、地権者の意向も踏まえた土地の有効活用をめざし、対話をさらに進めます。令和7年度中には土地区画整理組合が設立される予定であり、府とも連携を密にしながら、本地区の活性化に向けて必要な支援を行うなど、取組を強化します。
さらに、少子化・高齢化、人口減少社会が進む将来を見据え、本市にふさわしい都市機能の強化、公共施設等の適正化、居住誘導の推進などを図り、中長期的な都市経営を実現するため、令和7年度に立地適正化計画を策定し、「コンパクトシティ」の形成という考えの下、持続可能なまちづくりを進めます。
まちづくりの観点から、市民病院跡地については、市民のご意見も踏まえ、地域の関係者や有識者などで構成される検討委員会で議論を深め、地域貢献と活性化につながる施設整備をめざします。
さらに、市域の快適な住環境の確保に向けて、生活道路を含む道路や水路の整備、空家対策、下水道の保全及び更新などについて、市民ニーズにも留意しながら、計画的に事業を進めます。
道明寺駅周辺については、歴史性や地域性を活かしたまちの魅力アップを図るため、地区住民の方々との協働により道明寺停車場線道路美装化工事を継続し、良好なまちなみ景観の整備を進めます。
これまで地元交通事業者等の関係者と検討を行ってきた公共交通のあり方については、学識経験者、関係団体、市民等で構成する藤井寺市地域公共交通会議において、公共施設循環バスの見直し、デマンドタクシーの導入などの調査審議が進められてきました。令和7年度はこれらの成果を取りまとめ、暮らしやすいまちづくりをめざした本市にふさわしい公共交通の導入に向けて、実証運行を行います。
空家対策は全国的にも喫緊の行政課題の一つです。空家の削減や発生の抑制に向けた普及啓発のほか、空家所有者に対しては適正な管理を促し、保安上の危険や周辺住環境に悪影響が生じるケースには、必要に応じ、強く指導するとともに、空家の利活用について国や府のほか、民間団体とも連携した取組を進め、安全安心な住環境づくりに努めます。
公共下水道に関しては、雨天時侵入水の対策計画策定業務を進めるほか、既設下水道管の老朽化対策としてコンクリート系管の状況調査を引き続き進めます。
以上、総合計画の5つの施策の柱に沿って、施策の概要を申し上げました。現下の厳しい財政状況の下で、これらを推進するためには、適切かつ機動的に施策遂行が可能な収支均衡型の財政構造への転換、それを支える職員の前向きな改革意識が不可欠です。このことについても、私の考えを申し添えたいと存じます。
6.持続可能な行財政運営と職場環境
本市の厳しい財政状況は改めて申すまでもありません。この難局を乗り越えるためには、まず歳出予算の見直しが必要です。社会保障関係の扶助費の大幅な拡大が当面続く中、令和7年度予算の編成にあたっては、削減すべきものは削減し、真に必要な予算を確保する「選択と集中」に意を用いました。市民の皆様にも歳出抑制についてのご理解を賜りたいと存じます。
一方で、歳入財源の拡大・多角化にも取り組みます。その中でもふるさと納税の取組は、自主財源の確保のみならず、地場産品の発掘や経済活性化にもつながることからその取組を一層強化します。企業版ふるさと納税についても企業から多く賛同をいただけるよう、寄附金に相応しい意義ある事業を広くPRしてまいります。
また、公共用地の有効活用については、短期、中長期の時間軸を置き、活用手法を含めてその可能性を検討します。
行政需要は多様化・肥大化する傾向にあり、職員の業務遂行に負担がかかりがちです。職員数にも制約がある中で、労働生産性の向上と省力化を実現するためには、行政機構の様々な箇所でDXの導入・活用が不可欠です。自治体DXの推進に向けては、国が全国で推進している自治体情報システム標準化への対応を着実に進めるとともに、AIも効果的に活用し、業務改善、業務効率化につなげられるよう、創意工夫してまいります。こうしたデジタル環境の形成においては、同時にセキュリティシステムの確立も必要とします。必要な対策と併せ、個人情報や機密情報に対する職員の意識醸成、情報リテラシーの向上に留意し取組を進めます。
自治体DX はまだ緒についたばかりですが、本市においてもLINE公式アカウントに拡充した公共施設の予約機能や、災害時の避難所へのチェックイン機能など、市民の皆様に活用していただく取組も開始いたしました。専門知識・技術を有する職員の育成も図りながら、市民サービスの向上に努めます。
こうした行政分野の新たな課題や懸案に対処していくためには、職員が長く踏襲された慣習や前例に縛られることなく、柔軟な発想の下で法令等の知識を正しく活かし、突破口を見出そうとする気概が求められます。令和8年度の実施を目途に制度構築を進めている評価結果の相対化を加えた人事評価制度については、令和7年度に試行実施を行います。また、改善に努めている3年から5年を目安とする一般職員の異動サイクルの定着や、組織のフラット化などと併せ、職員のモチベーション向上につながるよう取組を進めます。
さらに、コンプライアンスやハラスメントといった観点においても、市職員としての自覚を持って行動できるよう研修等の機会を通じ、その認識を再確認させ、法令の遵守と綱紀粛正について、その徹底を図ります。
こうした取組を通じ、全ての職員がそれぞれに有する個性や能力を発揮し、充実したワークライフバランスと働きやすい職場環境が実現されるよう努めます。
むすびに
最後に、冒頭申し上げましたように、令和7年度は新たなアイセルシュラホールが船出します。市民の皆様との協働・共創により、「笑顔と活気に満ちた快適なまち」の実現に向け、私が先頭に立ち、現状とめざすべき方向を明確にし、職員共に一丸となり、舵をしっかりと取ってまいります。
市民の皆様並びに議員の皆様におかれましては、引き続き、格別のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げ、令和7年度の市政運営方針といたします。
- お問い合わせ
-
政策企画部 政策推進室戦略調整課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所5階52番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1171 (総合調整・事業管理担当、企画推進担当)
ファックス番号:072-952-9501
メールフォームでのお問い合せはこちら