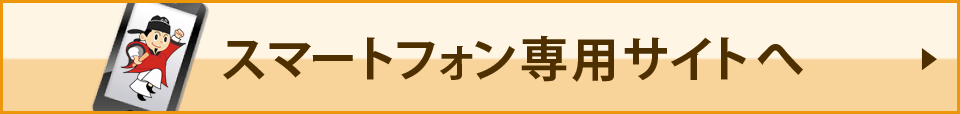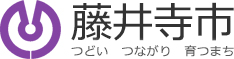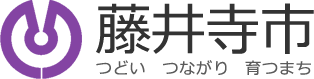子どもの予防接種
更新日:2025年10月09日
各項目をクリックすると、該当の説明箇所へジャンプします。
4種混合ワクチンの販売終了に伴い、医療機関での在庫がなくなり次第、4種混合ワクチンでの接種ができなくなります。
4種混合ワクチンの計4回の接種が完了していない方で、4種混合ワクチンでの接種が難しい場合は医師と相談のうえ接種を進めてください。
1. 4種混合ワクチンとヒブワクチンの残りの回数が同一の場合
→ 5種混合ワクチンに切り替えて残りの回数を接種することができます。
2. 4種混合ワクチンの残りの接種回数が、ヒブワクチンより多い場合
→ 4種混合ワクチンの不足分を、「3種混合ワクチン+不活化ポリオワクチン」
で接種することができます。
また、令和7年7月25日付 厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部予防接種課からの事務連絡において、「すでに接種されたヒブワクチンの回数によらず、5種混合ワクチンを用いて予防接種を完了することとして差し支えない。」と通知がありました。
そのため、上記2.の場合でも5種混合ワクチンで接種することができます。
医師と相談のうえ、接種をお願いいたします。
3種混合ワクチンや不活化ポリオワクチンの予診票が必要な場合、健康・医療連携課までお問合せください。
3種混合ワクチン → ジフテリア・百日せき・破傷風の混合ワクチン
4種混合ワクチン → ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオの混合ワクチン
5種混合ワクチン → ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ・ヒブの混合ワクチン
予防接種のタイミングは、感染症にかかりやすい年齢などをもとに決められています。お子さんの健やかな成長のために遅らせずに予定通り受けましょう。
〇厚生労働省HP 「遅らせないで!子どもの予防接種と乳幼児健診」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11592.html
予防接種一覧
標準的な予防接種スケジュール
対象年齢と標準的な接種時期について
対象年齢
公費で接種が受けられる期間です。自己負担はありません。対象年齢を過ぎた場合や、項目にない予防接種は希望者が全額自己負担で実施する「任意接種」となりますのでご注意ください。
標準的な接種時期
対象年齢のうち、より接種が望ましい時期として示されている期間です。
各項目をクリックすると、該当の説明箇所へジャンプします。
ロタウイルスワクチンには、ヒトロタウイルスを弱毒化した 1 価ワクチン(ロタリックス)とウシ‐ヒトロタウイルスを再集合させた 5 価ワクチン(ロタテック)があります。
|
標準的な接種時期 (望ましい接種時期) |
対象年齢 (公費での接種が可能な期間) |
|
|
1 回 目 |
ロタリックス・ロタテックいずれも、 生後2か月~14週6日後まで ※腸重積症の好発時期を避けるため、14週6日までに接種してください。 |
【ロタリックス】 生後6週0日後から24週0日後まで
【ロタテック】 生後6週0日後から32週0日後まで
|
|
2 回 目 以 降 |
【ロタリックス】 ・生後24週(約5か月半)までに、1回接種 ・前回接種より27日以上間隔をあける 【ロタテック】 ・生後32週(約7か月半)までに、2回接種 ・前回接種よりそれぞれ27日以上間隔をあける |
予診票は、こんにちは赤ちゃん事業(生後2か月頃に行われる看護師等によるご自宅への訪問)にてお渡しします。
小児用肺炎球菌の予防接種について (PDFファイル: 52.4KB)
|
標準的な接種時期 (望ましい接種時期) |
対象年齢 (公費での接種が可能な期間) |
|
|
初回 (3回) |
・生後2か月~7か月未満の間に接種開始 ・生後12か月までに3回接種 ・接種間隔はそれぞれ27日以上あける |
生後2か月~5歳未満 |
|
追加 (1回) |
初回接種3回終了後、60日以上の間隔をあけ、かつ1歳を過ぎてから1回接種 |
予診票は、こんにちは赤ちゃん事業(生後2か月頃に行われる看護師等によるご自宅への訪問)にてお渡しします。
小児用肺炎球菌の予防接種は、接種開始年齢によって、接種回数が違います。標準的な接種時期から外れた場合の接種方法は、下記を参照してください。
【小児用肺炎球菌:標準的な接種時期を過ぎた場合の接種方法】 (PDFファイル: 319.9KB)
B型肝炎予防接種について (PDFファイル: 66.0KB)
|
標準的な接種時期 (望ましい接種時期) |
対象年齢 (公費での接種が可能な期間) |
|
|
1回目 |
生後2か月~9か月未満の間に接種 | 1歳未満 |
| 2回目 | 1回目接種より27日以上あけて接種 | |
|
3回目 |
1回目接種から139日(20週)以上あけて接種 |
予診票は、こんにちは赤ちゃん事業(生後2か月頃に行われる看護師等によるご自宅への訪問)にてお渡しします。
※母子感染予防のため出産後すぐに接種を開始した場合は、健康保険の適用となるため、定期接種の対象外となります。
※ご家族からの感染リスクが高く(母子感染予防を除く)、医学的に必要と判断される場合は、生後2か月以前の早期の接種も定期接種として取り扱うことが可能です。早期に接種された場合は、健康・医療連携課にご相談ください。
5種混合予防接種について (PDFファイル: 66.6KB)
|
標準的な接種時期 (望ましい接種時期) |
対象年齢 (公費での接種が可能な期間) |
|
|
初回 (3回) |
生後2か月より接種開始し、生後12か月までに3回接種 接種間隔はそれぞれ20日以上あける |
生後2か月~7歳6か月未満 |
|
追加 (1回) |
初回接種3回終了後、1年以上の間隔をあけてから1回接種 |
予診票は、こんにちは赤ちゃん事業(生後2か月頃に行われる看護師等によるご自宅への訪問)にてお渡しします。
令和6年4月より5種混合が定期接種になりました。
4種混合とヒブを接種した場合は、追加接種終了まで原則同一ワクチンで進めてください。
4種混合予防接種について (PDFファイル: 181.5KB)
4種混合ワクチンは5種混合ワクチンからヒブワクチンを除いたものです。接種回数、接種間隔は5種混合ワクチンと同じです。
4種混合ワクチンの販売終了に伴い、医療機関での在庫がなくなり次第、4種混合ワクチンでの接種ができなくなります。詳細は【お知らせ】をご確認ください。
|
標準的な接種時期 (望ましい接種時期) |
対象年齢 (公費での接種が可能な期間) |
|
|
初回 (3回) |
生後2か月~7か月未満の間に接種開始し、生後 12か月までに3回接種 接種間隔はそれぞれ27日以上あける |
生後2か月~5歳未満 |
|
追加 (1回) |
初回接種3回終了後、7か月以上の間隔をあけ、かつ 1歳を過ぎてから1回接種 |
予診票は医療機関にあります。
ヒブの予防接種は、接種開始年齢によって、接種回数が違います。標準的な接種時期から外れた場合の接種方法は、下記を参照してください。
【ヒブ:標準的な接種時期から外れた場合の接種方法】 (PDFファイル: 314.5KB)
BCG予防接種について (PDFファイル: 168.0KB)
| 接種回数 |
標準的な接種時期 (望ましい接種時期) |
対象年齢 (公費での接種が可能な期間) |
| 1回 | 生後5か月から生後8か月未満 | 1歳未満 |
予診票は、こんにちは赤ちゃん事業(生後2か月頃に行われる看護師等によるご自宅への訪問)にてお渡しします。
水痘(水ぼうそう)予防接種について (PDFファイル: 65.5KB)
|
標準的な接種時期 (望ましい接種時期) |
対象年齢 (公費での接種が可能な期間) |
|
|
1回目 |
1歳から1歳3か月の間に接種 | 1歳から3歳未満 |
|
2回目 |
1回目の接種後、6か月以上の間隔をあけて接種 |
予診票は、こんにちは赤ちゃん事業(生後2か月頃に行われる看護師等によるご自宅への訪問)にてお渡しします。
注意1:任意接種で過去に1回接種された方は、残り1回接種できます。
過去に2回接種された方は、接種の必要はありません。
注意2:過去に水痘にかかった方は、接種の必要はありません。
ワクチンの供給が不安定な状況により、接種対象期間内に定期接種を受けられなかったかたがいる可能性があることから、下記のかたは令和7年4月1日から令和9年3月31日まで定期接種期間が延長されることとなりました。
1.麻しん・風しん(MR)ワクチン1期
令和4年4月2日から令和5年4月1日生まれで麻しん・風しん(MR)ワクチン1期を未接種のかた
2.麻しん・風しん(MR)ワクチン2期
平成30年4月2日から平成31年4月1日生まれで麻しん・風しん(MR)ワクチン2期を未接種のかた
麻しん・風しん予防接種について (PDFファイル: 80.9KB)
|
標準的な接種時期 (望ましい接種時期) |
対象年齢 (公費での接種が可能な期間) |
|
|
第1期 |
1歳になったらすぐ | 1歳から2歳未満 |
|
第2期 |
5歳から7歳未満 (年長期:小学校就学前1年間) |
5歳から7歳未満 (年長期:小学校就学前1年間) |
予診票は、こんにちは赤ちゃん事業(生後2か月頃に行われる看護師等によるご自宅への訪問)にてお渡しします。
日本脳炎予防接種について (PDFファイル: 64.3KB)
|
標準的な接種時期 (望ましい接種時期) |
対象年齢 (公費での接種が可能な期間) |
|
|
1期 初回 (2回) |
3歳~4歳前日までに2回接種 接種間隔は6~28日あける |
3歳から7歳6か月未満 |
|
1期 追加 (1回) |
1期初回(2回)接種後、おおむね1年の間隔をあけて1回接種 |
3歳から7歳6か月未満 (1期初回2回目接種より6か月以上空ける) |
|
2期 (1回) |
9歳~10歳前日までに1回接種 | 9歳から13歳未満 |
1期(3回分)の予診票は、こんにちは赤ちゃん事業(生後2か月頃に行われる看護師等によるご自宅への訪問)にてお渡しします。
2期(1回分)の予診票は、9歳のお誕生日月の月末にご自宅へ発送いたします。
※1期初回の標準的な接種期間は、3歳に達してからとされていますが、ご希望の方は、生後6か月から接種が可能です。医療機関にご相談ください。
日本脳炎の特例措置について
1期と2期合わせて計4回を接種していない方:平成19年4月1日以前に生まれた20歳未満の方
回数:4回の不足分
注意事項:20歳未満までに計4回
2種混合予防接種について (PDFファイル: 170.0KB)
| 接種回数 |
標準的な接種時期 (望ましい接種時期) |
対象年齢 (公費での接種が可能な期間) |
| 1回 | 11歳から12歳未満 | 11歳から13歳未満 |
予診票は、11歳のお誕生日月の月末にご自宅へ発送いたします。
ワクチンは3種類あります。いずれか1種類を接種してください。
ワクチンは原則同じ種類のワクチンで実施してください。
積極的勧奨再開について
ワクチンを接種後に、因果関係が不明な、持続的な疼痛などの副反応報告があったため、平成25年6月から国の方針により積極的な勧奨を差し控えてきました。しかし、その後の調査等において、子宮頸がん予防ワクチンの安全性について、特段の懸念が認められないことが確認され、接種による有効性が副反応のリスクを明らかに上回ると認められたことから、令和3年11月26日より積極的な勧奨が再開されることとなりました。
これにより、当市においても、子宮頸がん予防ワクチンの供給状況や接種体制を踏まえ、対象となる方への積極的勧奨を令和4年度から順次再開しました。対象の方には4月はじめに案内を送付しています。
また、これまで積極的勧奨の差し控えにより、接種機会を逃した方に対しても、接種機会を設けています。下記キャッチアップ接種をご覧ください。
子宮頸がん予防接種について (PDFファイル: 74.1KB)
| 接種回数 |
標準的な接種時期 (望ましい接種時期) |
対象年齢 (公費での接種が可能な期間) |
|
2~3回 |
中学1年生 |
小学校6年生~高校1年生相当の女子 |
予診票は、小学校5年生3月末頃にご自宅へ発送いたします。
接種するワクチンの種類により接種回数は異なります。下記をご確認ください。
接種間隔
※ワクチンは3種類あります。どれか1種類を接種してください。
<サーバリックス(2価ワクチン)>
1回目接種から1か月後、6か月後の各1回(合計3回)
<ガーダシル(4価ワクチン)>
1回目接種から2か月、6か月後の各1回(合計3回)
<シルガード9(9価ワクチン)>
【1回目の接種を15歳になるまでに受ける場合】
1回目接種から6か月後 (合計2回)
【1回目接種を15歳になってから受ける場合】
1回目接種から2か月後、6か月後の各1回(合計3回)
注意:厚生労働省がお薦めしている接種対象者は、中学1年生から高校1年生相当までの女子です。
子宮頸がん予防ワクチン(キャッチアップ接種)
(追記)キャッチアップ接種等の期間が条件付きで延長されます。
昨夏以降の大幅な需要増により、子宮頸がん予防ワクチンの接種を希望しても受けられなかったかたがいらっしゃる状況等を踏まえ、下記のような内容の延長措置を国の審議会で了承されました。
延長の内容
延長対象者 平成9年4月2日から平成21年4月1日生まれの女子で令和4年4月1日
から令和7年3月31日までに子宮頸がん予防ワクチンを1回以上接種し
接種完了していないかた
延長措置・期間 令和7年4月1日から令和8年3月31日の1年間に、残りの回数
(2回目、3回目)が公費接種できます。
厚生労働省ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou28/index.html
「ヒトパピローマウイルス感染症(HPVワクチン)」(厚生労働省)
子宮頸がんとHPVワクチンに関する正しい理解のために(公益社団法人 日本産婦人科学会)
要予約
医療機関で受ける予防接種は、1年を通じて受けられます。
ワクチンの流通量には限りがあり、希望してもすぐに接種できない場合があります。
かかりつけの医療機関窓口でお尋ねください。
1.母子健康手帳
2.予診票
予診票をお持ちでない方は、健康・医療連携課までご連絡ください。
※接種費用は無料です。
下記に該当するかたは接種できません。該当しないかご確認してください。
- 母子健康手帳を持っていない。(子宮頸がん予防ワクチンは除く)
- 当日体調が悪い。(予防接種は体調が良い時に受けるのが原則です。)
- 明らかに発熱(通常37.5℃以上)している。(接種日の朝は、必ず体温を測定してください。)
- 重い急性疾患にかかっていることが明らかである。
- 接種しようとする予防接種の接種液の成分によってアナフィラキシー(接種後約30分以内 に起こるひどいアレルギー反応)を起こしたことが明らかである。
- 日本脳炎特例措置(13歳以上)・子宮頸がん予防ワクチンの対象で、妊娠していることが明らかである。
- 注射生ワクチンで、前に接種した注射生ワクチンとの間隔が27日(4週間後の同じ曜日)以上空いていない。
予防接種の種類:BCG・麻しん風しん(MR)・水痘(みずぼうそう)など - 同じワクチンを2回以上接種する際、定められた間隔が空いていない。
- 病気などから期間が空いていない。 主治医の判断により、前後する場合があります。
|
病気など(状態) |
接種できない期間 |
|
麻しん、風しん、おたふくかぜ、水ぼうそう、肺炎 など |
かかってから4週間以内 |
|
きょうだいなどが上記の病気にかかり、うつる可能性のある方 |
かかってから2~3週間以内 (おたふくかぜは4週間以内) |
|
手足口病、へルパンギーナ、突発性発疹、 腸管系ウイルス性疾患、インフルエンザ など |
かかってから3週間以内 |
|
兄弟などが上記の病気(突発性発疹は除く)にかかり、うつる可能性のある方 |
かかってから2週間以内 |
その他、医師が接種不適当な状態と判断した場合
ご留意点
お子さんの体調の良い時に受けられるものから順に、計画的に接種してください。
接種間隔などわからないことがございましたら、健康・医療連携課までご相談ください。
心臓病・腎臓病・肝臓病、血液の病気や発育障害などで治療を受けている方や、過去にけいれん(ひきつけ)を起こし、現在も抗けいれん剤を使用している方などは、藤井寺市の予防接種委託医療機関での接種が可能か、主治医にご相談ください。可能な場合は、母子健康手帳の予防接種ページの余白にコメント記入いただくか、意見書を作成いただけるよう、主治医に依頼してください。上記の病気等で、他市町村での接種が必要な場合は、健康・医療連携課へご相談ください。
定期の予防接種は、生後2か月から開始されます。里帰りなど、やむを得ない事情により藤井寺市外で定期予防接種を希望される場合、接種前に必ず健康・医療連携課にお問い合わせください。詳細についてご説明いたします。
定期予防接種の対象者であった期間に、長期療養を必要とする疾病等の特別な事情により定期予防接種を受けることができなかった方については、予防接種法の対象年齢外であっても予防接種を受けられる場合があります。
対象の方は医師が接種可能と判断してから2年間は、定期予防接種として受けることができます。(予防接種の種類によっては上限年齢有)
特例措置に該当すると思われる方は、健康・医療連携課にご相談ください。
対象者
以下の条件を全て満たしている方
1 接種時に藤井寺市に居住している方
2 長期療養を必要とする重篤な疾病(下記「該当する疾病について」を参照)にかかったこと等により、やむを得ず定期予防接種を対象年齢内に受けられなかった方
対象期間
主治医が接種可能と判断した日から2年(接種上限年齢の定められている予防接種有)
接種上限年齢の定められている予防接種
BCG:4歳に達するまで
四種混合:15歳に達するまで
ヒブ:10歳に達するまで
小児用肺炎球菌:6歳に達するまで
対象となる予防接種
やむを得ず対象年齢内に接種できなかった種類の予防接種
(対象年齢内に接種したワクチンの再接種等は対象外です)
該当する疾病について
次の1~3に該当する疾病にかかり、やむを得ず定期の予防接種を受けることができなかった方
1.ア)重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫機能に支障を生じさせる重篤な疾病
イ)白血病、再生不良貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病
ウ)ア又はイの疾病に準ずると認められるもの
※該当する疾病の一例(下記「該当する疾病について」を参照)
2.臓器移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受け、やむを得ず定期の予防接種を受けることができなかったこと
3.医学的知見に基づき、上記に準ずると認められること
定期予防接種による健康被害によって引き起こされたと認定された副反応により、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障ができるような障害を残すなどの健康被害が生じた場合には、健康被害の程度に応じて予防接種法に基づく補償を受けることができます。
詳しくはこちらをご覧下さい。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_kenkouhigaikyuusai.html
任意予防接種による健康被害
任意予防接種によって引き起こされたと認定された副反応により、重篤な健康被害が生じた場合には、独立行政法人 医薬品医療機器総合機構法の「医薬品副作用被害救済制度」の救済を受けることができますが、予防接種法の制度とは救済の対象、額などが異なります。
詳しくはこちらをご覧ください。
- お問い合わせ
-
健康福祉部 健康・医療連携課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所2階25番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1112 (成人保健担当、母子保健担当、庶務担当)
072-939-1352 (旧市民病院整理室)
ファックス番号:072-939-9099
メールフォームでのお問い合せはこちら
- みなさまのご意見をお聞かせください
-