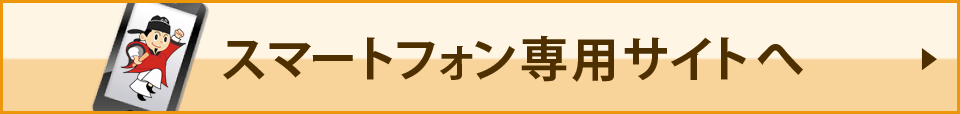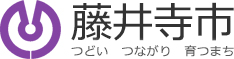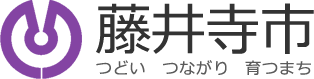主役は鉄器(No.16)
更新日:2013年12月19日

棺おけの内部の発掘を前に、わたしたちの緊張はいやがうえにも高まってきました。これまでの調査例や、一部に露出した鉄剣の状態から推測すると、発掘が進めば、大量の遺物の出土が予測されたのです。
土層観察用のアゼを残して、竹ベラを使って慎重に土をはねていきました。土層観察用のアゼは、土層の堆積状態を見ながら、発掘の進め方に誤りがないかどうか点検する重要な役割ももっているのです。
発掘を進める中で、いろいろなことが分かってきました。その一つは、棺おけは、石や粘土などで特別な保護施設を作らず、大きな墓穴の中に直接置いて埋め戻されていたこと。もう一つは、棺おけは長方体の箱形をしており、その中にはびっしりと鉄製品が納められていたこと。東側の箱には、鉄の刀と剣が5群に分けて入れられ、南北両端には短剣が入っていました。
西側の箱は、短剣が両端に入っていることは東側の箱と共通していたのですが、箱の中央からは鉄製の農具や工具類が大量に出土したのです。
一方で、大きな疑問も生まれました。
それは、これまで棺おけといってきたように、人体の埋葬を予想していたのですが、どうもその痕跡が見当たらないことなのです。古墳は、特殊ではありますが、墓の一種と定義されています。もちろん、埋葬された人体そのものが残っていることは、まれなことです。しかし、人体に塗られた朱や、ネックレスにしていた玉、生前大切にしていた鏡などの宝物が一緒に出土することから、人体埋葬があったことを知ることができるのです。西墓山古墳では、人体埋葬があったことを積極的に証明する事実が、全く得られなかったのです。
次に考えられることは、この施設のほかに、人体埋葬用の施設が存在するのではないかということです。しかし、一辺18メートルの小規模な古墳では、見つかった施設を中央にとると、ほとんどその余地のないことがはっきりするのです。古墳のすべてを発掘しているわけではないので、ほかに埋葬施設が絶対ないとは断言できないのですが、少なくとも西墓山古墳の主役は、この鉄器埋納施設であることは疑いのないところでしょう。
発掘はどんどん進み、鉄器に埋まった内部の全貌がほぼ明らかになってきました。
気になりだしたのは、鉄器のサビが思いのほかひどい点なのです。
写真:掘り上がった鉄器埋納施設
『広報ふじいでら』第266号 1991年7月号より
- お問い合わせ
-
教育委員会事務局教育部 文化財保護課
〒583-8583
大阪府藤井寺市藤井寺3丁目1番20号アイセルシュラホール2階
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1419 (文化財担当、世界遺産担当)
ファックス番号:072-952-7806
- みなさまのご意見をお聞かせください
-