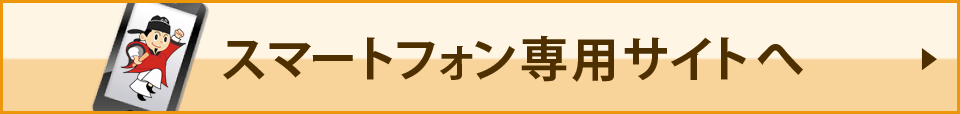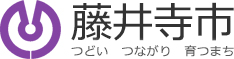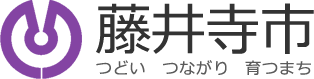史跡古市古墳群唐櫃山古墳の調査成果について
更新日:2020年12月24日
史跡古市古墳群内では、標記の古墳について、整備事業に伴い確認調査を実施し、下記のとおり成果がありましたので報告します。
(報道提供日時:2020年12月24日14時0分)
経緯・経過
今回の発掘調査は、唐櫃山古墳の史跡整備に伴い、令和2年9月から実施しています。
所在地
藤井寺市国府1丁目
調査成果の概要
墳丘の北側及び東側で発掘調査をおこない、唐櫃山古墳の墳丘及び周濠部分、允恭天皇(いんぎょうてんのう)陵(市野山)古墳の堤を確認しました。
唐櫃山古墳の周濠の形状は従来考えられていた盾形のものではなく、前方部に向かって狭まる形状を呈するものと考えられます。
墳丘北側にあたる、允恭天皇陵古墳の堤では堤上面に敷かれたような石(敷石)を確認しました。古墳の堤にあたる部分で敷石の可能性が高く、大規模な前方後円墳の築造を考えるうえで重要な成果といえるでしょう。
調査成果のまとめ
今回の調査成果からは、唐櫃山古墳の周濠形状が従来想定されていた形状と異なることや、主墳である允恭天皇陵(市野山)古墳との接続箇所及び堤上面の様相が確認できました。
唐櫃山古墳の周濠形状は従来盾形の周濠が巡るものと考えられていましたが、今回見つかった周濠は従来の想定よりも墳丘に近しい位置で確認されました。このことは、周濠の形状が前方部側は狭まることを意味しています。類似する形状をもつ古墳は堺市の孫太夫古墳(帆立貝式前方後円墳、全長56m)や収塚古墳(帆立貝式前方後円墳、全長57.7m)などがあります。また、唐櫃山古墳の堤に落ち込みが見られず、允恭天皇陵(市野山)古墳の堤に取り付くように築造されたと想定されます。唐櫃山古墳が取り付くように築造されたということは、允恭天皇陵(市野山)古墳と一体性をもって築造されたと考えられます。
そのほか、允恭天皇陵(市野山)古墳の堤上に敷かれたと思われる石を確認しました。堤上に敷石を施す例は仁徳天皇陵(大山)古墳(前方後円墳、全長486m、大阪府堺市)やヒシアゲ古墳(磐之姫命陵、前方後円墳、奈良県奈良市)で確認されています。
その他
新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、現地公開は実施しません。ご理解ご協力をお願いします。
唐櫃山古墳
唐櫃山古墳は、古市古墳群の北東部に位置する全長59mの帆立貝式前方後円墳です。5世紀後半に築造されました。古墳の北側に隣接する同時期の前方後円墳、允恭天皇陵(市野山)古墳の陪冢(ばいちょう)の一つと考えられています。後円部墳頂より竪穴式石槨(たてあなしきせっかく)に納められた刳貫式家形石棺(くりぬきしきいえがたせっかん)は、阿蘇産の溶結凝灰岩(ようけつぎょうかいがん)を用いています。
唐櫃山古墳の以前おこなわれた発掘調査では、1段目斜面の葺石は前方部側でのみ確認されており、後円部には葺いていなかったものと考えられます。そのほか、後円部の1段目では円筒埴輪列が確認されています。
資料
唐櫃山古墳調査成果の図 (PDFファイル: 670.7KB)

唐櫃山古墳北側調査区(南より)

第2調査区で確認された堤上に敷かれたと思われる石(南より・奥は允恭天皇陵(市野山)古墳)

墳丘上に敷かれたと考えられる石
(北より・奥は唐櫃山古墳)

唐櫃山古墳墳丘と周濠、堤部分(西より)
- お問い合わせ
-
教育委員会事務局教育部 文化財保護課
〒583-8583
大阪府藤井寺市藤井寺3丁目1番20号アイセルシュラホール2階
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1419 (文化財担当、世界遺産担当)
ファックス番号:072-952-7806